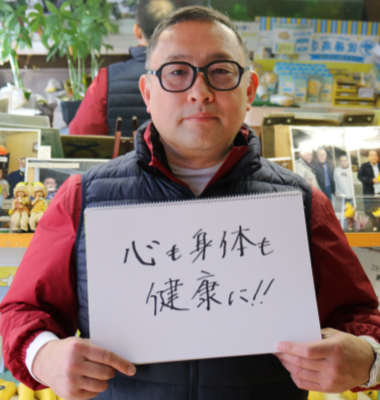美味しいバナナで
地元に愛される会社
バナナ専門で94年
佐藤商店は、バナナ問屋として私の祖父が1931年(昭和6年)にこの場所で創業しました。創業当初からバナナの卸売りと小売りを続けて今年で94年になります。扱っているバナナは、フィリピン産、エクアドル産、台湾産と3つの産地の物を中心に販売しています。
バナナの仕入れは現地に出向いて直接買い付ける事は難しいので、商社を経由して2週間に3回位のペースで入荷してきます。入荷したバナナはまだ青い状態で「ムロ」という空調が付いた倉庫に保管し、温度と湿度を管理して出荷タイミングに合わせて丁度良い熟成状況にして販売します。
熟成したバナナは、地元スーパーや小売店、道の駅、更に一部大手スーパー、イベントなどで販売されるスポット的な卸売りの他、店頭での小売りもしています。昔は卸の方が多かったですが、現在は卸で6.5割、小売りで3.5割位になっています。
小売は基本的に地元のお客様が中心でしたが、ここ10年前位からテレビなどのメディアで紹介していただく機会が増えて、遠くから買いに来てくださるお客さまも増えました。私と母の2人だけでやっているので、卸売りと店頭での小売り以上の対応はできませんが、うちで熟成したバナナを「佐藤商店のバナナ」としてイベントなどで販売したり、ジュースやソフトクリームにして販売してくださっています。また他にもコラボ商品としてうちのバナナを使って「バナナオレ」「バナナオレポップコーン」「リーフパイ」なども販売されています。
スーパーで販売しているバナナと当社のバナナの違いをよく訊かれますが、仕入れているまだ青いバナナはほぼ変わらない物だと思います。スーパーなどにバナナを卸している会社の方が、コンピュータで管理され温度や湿度も自動的に変化するなど設備が整っていて、その方がよほど良い物が出来るのではないかと思います。
バナナの熟成は温度と湿度の管理で、それでも違うと言っていただけるのは、職人というか「勘」の部分が機能している事と、だいぶ古くなってしまった設備が、逆にバナナを熟成させる「良い環境」になっているのかもしれません。
入荷してくるバナナは船で運ばれている間に熟してしまわないように、ガスを入れた袋に入れて箱詰めで届き、その袋を開封して「ムロ」に入れると熟成がスタートします。「ムロ」に積み上げたバナナが入った箱は、ずらして積み上げて通気できるようにしています。なるべく時間をかけ、木になっているのと同じように、徐々に色が出てくるように温度なども気を使うよう心掛けて熟成させる事でバナナが美味しく熟成します。

次々とお客様が訪れる店舗
店舗には佐藤商店のバナナを使ったコラボ商品が並ぶ
熟成の技術を見て学ぶ
私もこの町で生まれ育ち、高校までは地元の学校へ通い、小学生から始めた剣道は今でも続けています。子供の頃から特に将来やりたい事もなく、高校を卒業して東京の大学に入って卒業しても館山には戻らずに、そのまま東京の出版関係の会社に就職し、営業の仕事をしていました。弟は、全く帰って来る事は考えていない様子で「後継ぎになる」と具体的に考えていなかったものの、長男の私は何となく考えてはいたので、はっきりと後を継ぐという覚悟を持たないまま30歳の時に館山に戻ってきました。
「後継ぎになる」という事もはっきりしないまま館山に戻った私ですが、2代目の父も自ら望んで後を継いだ訳ではありませんでした。父は私と違って次男だったので、後を継ぐつもりなどなかったそうです。当時にしては体が大きい方だった父は、高校時代に証券会社の実業団のバスケットボールチームにスカウトされ、選手をしていました。ある時祖父から「お前が後を継げ」と呼び戻され、その結果後を継ぐことになったそうです。そんな2代目の父も、コロナ禍の最中に体調を崩してお客様とあまり接触する事が出来ないまま亡くなったのが今から4年前の事でした。館山に戻った父は30年以上前からミニバスケットボールのチームを自分で作っていました。商売に関しては私がいたというのもあったと思いますが、商売ができなくなるより、バスケットボールが出来なくなった事の方を悔しがっているほどでした。なので葬式の時には過去の教え子たちが「こんなにいたんだ」というほど来てくれました。父が亡くなって商売の方は母と私の二人で切り回すようになり、正式に3代目としてやっていく事になりました。
輸入されたバナナは、良い状態で段ボール箱に入っているものばかりではなく、更にバナナの状態も同じではありません。またそれを見極めるためのマニュアルもありません。バナナを触ったり、見たりする事で状態を見極め、出荷のタイミングも計算した上で温度や湿度などを試行錯誤しながら設定します。このやり方は祖父の時代から続いている方法で、私も父や母がやっているのを見て、教わるというより「見て学べ」という方法で父母がやっている事を覚えていきましたが、データを取る事も出来ず、今でも何となく「こうかな」と試行錯誤しながらその時の判断で、母と相談しながらやっています。
店舗に飾られている3代続くバナナ問屋「半纏」
青いバナナの状況を見て熟成までの過程を計算する